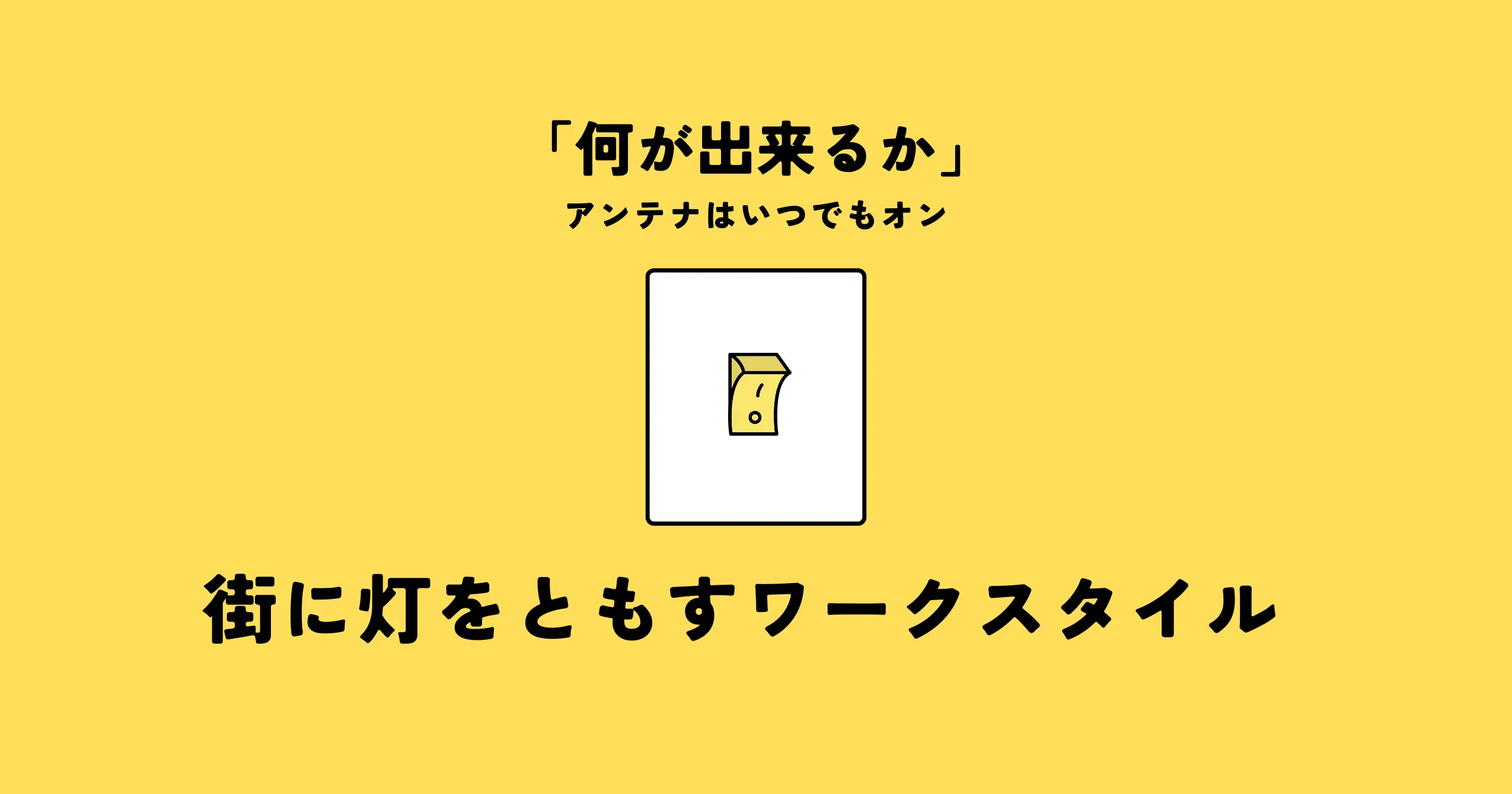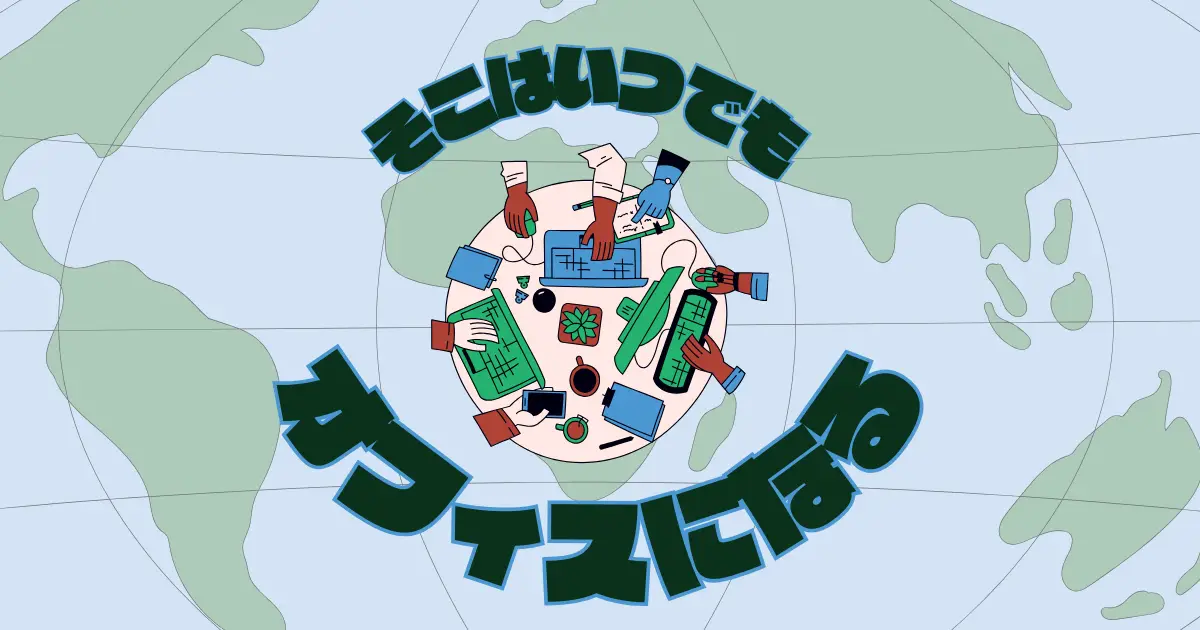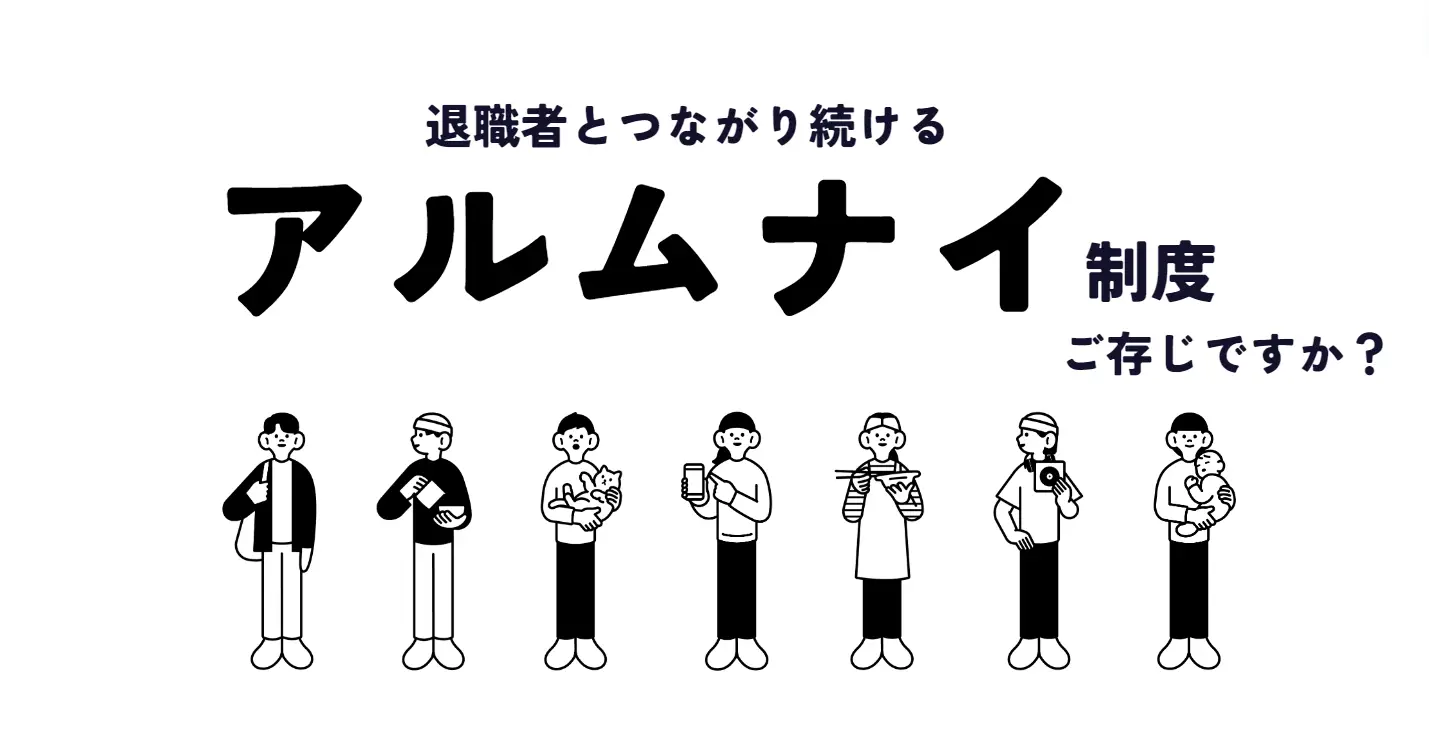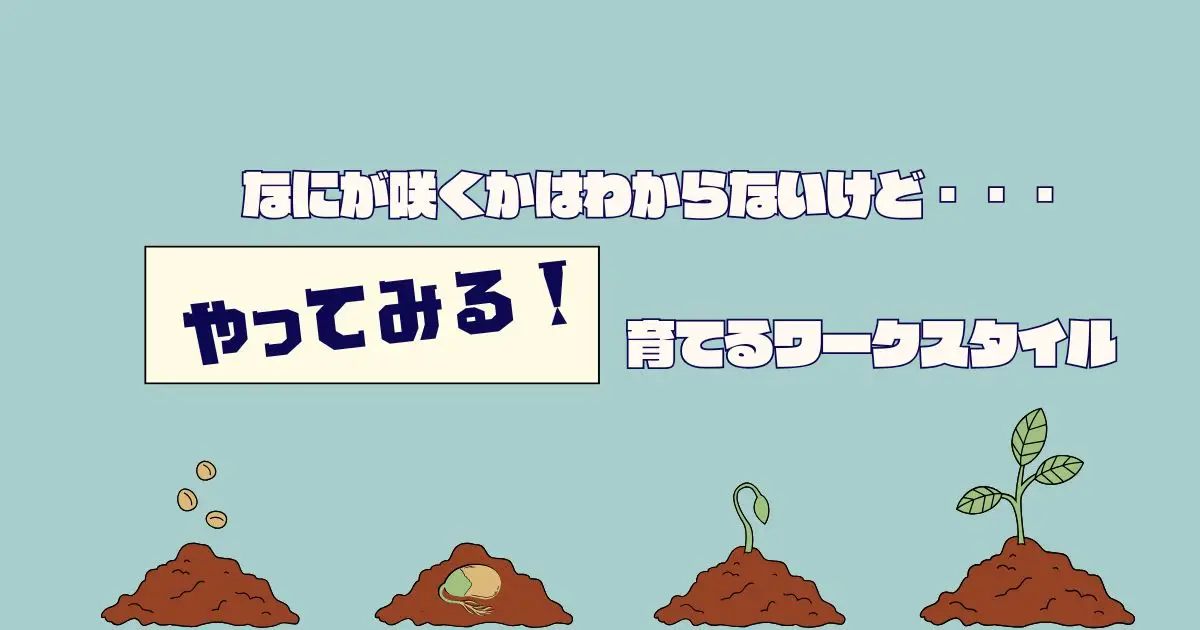
「あなたの会社のお菓子だから買いたい!」商品ではなく会社を好きになってもらうために立ち上がった部署のおかしな(?)ワークスタイルとは
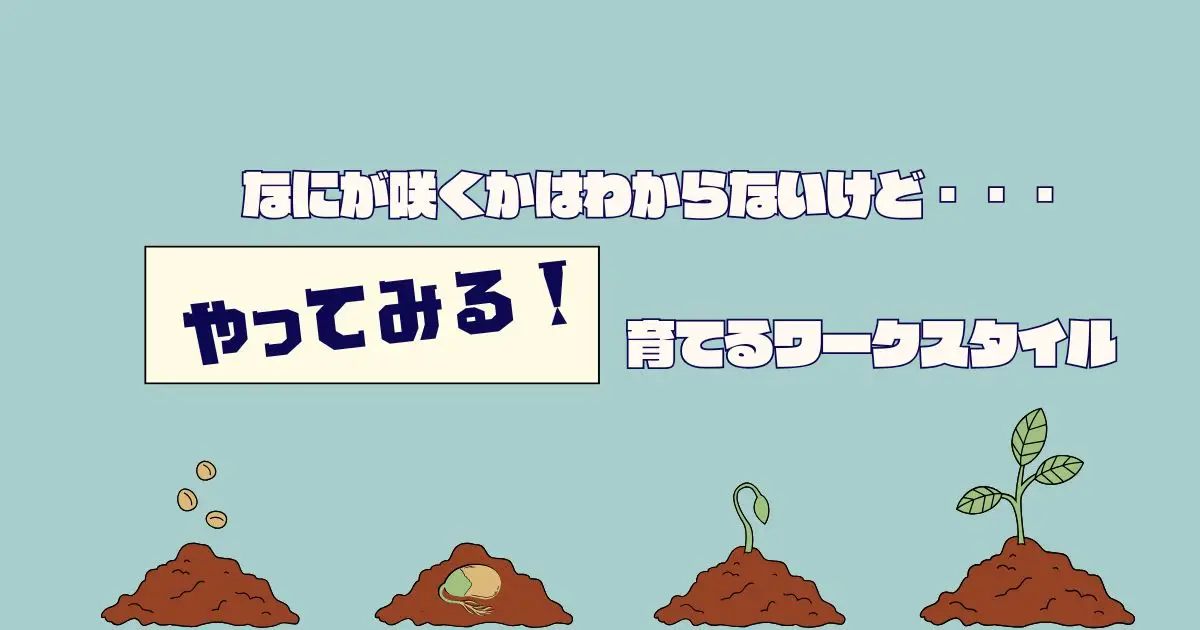
名古屋を代表するお菓子メーカー春日井製菓は、2022年に「おかしな実験室」というユニークな部署を立ち上げました。ちょうどそのタイミングで同社に入社し、新しい取り組みを実現してきた高木宏幸さん。コラボベースNAGOYA(コラボスタイルが運営する会員制ソーシャルワークスペース)の会員でもあり、いつも生き生きと仕事する姿を見せてくださいます。仕事を楽しむその秘訣とは?
ゼロからはじめた畑での研修会
高木さんの現在のお仕事を教えてください。
一般的な役割で言えば「おかしな実験室(以下、おか験)」は「コーポレートコミュニケーション/企業広報」を担う部署です。簡単に言えば、「春日井製菓を仲間と思ってもらう」ための活動をしています。また、新規事業を創出する部署でもあります。
「春日井製菓っていいよね、面白いよね」と生活者に思ってもらえたら、商品も手に取ってもらいやすくなる。そのために、これまでにない取り組みを試行錯誤しています。
なかでも続けて良かったと思う活動は?
春日井市にあるおかしな実験農場で行っている月に1回の「畑と自分を育てる日」のプロジェクトですね。
 Photoby 野村優
Photoby 野村優
看板商品のひとつ「グリーン豆」が2023年で発売50周年を迎えたため、原材料のエンドウ豆を自分たちで育ててみよう、というコンセプトで始まりました。原料はずっと輸入しているので、長い間グリーン豆をつくっていても、(家庭菜園で栽培している人以外)社内の多くの人は生の豆が育つ様子を見たことがなかったんです。
とはいえ、就業時間中に畑仕事をするのは、当社にとっては前代未聞。育てた豆を原材料に使うなら生産活動の一環と言えますが、そうでない活動に社内の仲間から「それは仕事なのか?」と疑念を抱かれかねません。そこで、当社が推し進める「人づくり・自分づくり」の方針に合わせ、午前は畑で農作業、午後は場所を移してビジネススキルを学ぶ月イチ研修と位置づけ、「畑と自分を育てる日」と命名しました。おかしな実験室はもとから「OPEN/FLAT/DIVERSITY」を大切にしているので、社内だけでなく社外の人も参加できるように開いてみたところ、社外の人の方が面白がってくれて、徐々に人数が増えていったのです。そして、この取り組みを進化させるために、私は「畑のコミュニティマネージャー」に任命されました。しかし、一体何をしたら良いのか、何をすれば当社を好きになってもらえるのか、まったくわかりませんでした。
当初の座学は、プレゼンテーションやファシリテーションや企画のやり方といったビジネススキルを教わるものでした。しかし、これは講師も準備が大変ですし、教わる側は受け身になりがちです。そこで、畑の日の参加者がリアルに抱えている仕事上の課題をテーマに、皆が学び合うスタイルに転換。私は課題提供者の選定と、事前ヒアリングによる悩みや問題の抽出、当日のワークショップのチーム分けと進行役となるよう、つくり直したのです。
すると、みなさん真剣に、のめり込むように取り組んでくれるようになりました。毎回10人程度だった参加者数が30人を超えたことも。育てたコンテンツが喜んでもらえるようになり、面白くなってきたのは最近のことです。
何もないところから始めて、成果が出るかわからない。そのなかで取組を続けるのは大変ですよね。
そうですね。でも、おか験の活動はすべて何もないところからはじめるものなので、大変ですが慣れました。それに、何をもって成果とするかは自分たちで定義しています。畑の場合は2つの成果目標を定めており、1つは畑で“仲間”を増やせるか。参加人数だけでなく、リピーターの割合等も見ています。
2つ目は会社の認知度を上げるために貢献できるか。SDGsや他社がやっていない取り組みをすることによってメディアにも注目されますから。
4つの業種で4つの職種を経験
高木さんのキャリアを教えていただけますか?
新卒で(株)富士通中部システムズ(現、富士通(株)) に入社し、東京でシステムエンジニア(SE)を6年半つとめました。元々私は文系で文学部を卒業したんですが、SEの人材ニーズが高い時代で、「カッコよさそう!」と思って飛び込みました。
最初の2年ほどは、プログラミングもやっていましたが、コミュニケーション能力を買われて、お客様への提案などの営業的な動きをするようになりました。受注のため日々奔走し充実した日々を送っていたのですが、SE職が営業で成果を上げても評価されにくい風土でした。
そこで、(株)リクルートエージェントに転職します。勤務地が選択できたので地元の名古屋に戻り、転職希望者に新天地を紹介するキャリアアドバイザーと、人を採用したい企業から求人を獲得する営業を担当しました。自分の肌に合っていたし、すごく熱い思いで仕事に取り組み、多くの人のキャリアチェンジを支援してきました。まわりの人にも恵まれ、やりがいもあったのですが、転勤が多かったことが問題でした。5年目を迎える頃、東京への異動が現実的になり、子どもが生まれて家も建てるなど名古屋にできていた生活の基盤を優先したいため、退職。次は、同朋学園(同朋大学、名古屋音楽大学、名古屋造形大学、同朋高等学校、同朋幼稚園を運営する学校法人)の職員になりました。リクルートでは転職支援に携わってきましたが、当時の大学にはキャリアの考え方を教えられる人がまだまだ少ないことに、問題意識を持っていました。そこで、学生のキャリア支援に関心を持ったのです。
ところが、入ってみると少子化で学生数の減少が深刻。当初は名古屋音楽大学のキャリア支援センターに配属してもらったのですが、入試広報に改善の余地があると感じたため、志願して異動。5年間で同朋大学と名古屋音楽大学の入試広報センターを立て直し、志願者数も大幅に回復させることができました。
それからキャリア支援に戻ったり、大学経営に関わるようにもなるのですが、内部的な事情でいろいろと思うところもあり退職しました。その後、リクルート時代の同僚の紹介で春日井製菓に入社し、今に至ります。
あえて多様な分野に飛び込んできたのでしょうか?
4業種4職種を経験しましたが、結果的にそうなっただけなので、「あえて」ではありませんね。しかし、職種をずらして経験することで、希少人材になれたかな、とは思っています。SEと人材紹介の営業と、大学の職員を経験したお菓子会社の広報は、他にはなかなかいないでしょう。
新しいものを生み出すためにしていること
春日井製菓さんには、はじめから広報として入社したのですか?
最初は人事部に紹介されたのですが、入試広報の経験があったことで、会社の広報を担う「おかしな実験室」という部署が新しくできるから、責任者に会ってみないか?と声がかかったのです。
「企業広報の経験はない自分に何ができるんだろう?」と戸惑いました。しかし、室長である原と面談して簡単な会話をすると、「ぜひ一緒にやろう!」と。「新しいことを実現したいが、いろいろ足りないものがある。そういう時に高木さんはどうしますか?」と訊かれたので、「ないものは つくればいいじゃないですか」と、私が軽く言ったことが、琴線に触れたようなのです。私は40代半ばからでも新しいことにチャレンジさせてもらえることが嬉しく、他にも今までの経験(人事・営業系)を活かせるような何社かに内定をいただいていたのですが、面談を終えてすぐお断りし、春日井製菓に入社しました。

コラボベースNAGOYAで高木さんとお会いすると、すごく毎日を楽しんでいるように感じます。
はじめてのこと、よくわからないことでも、実際にやってみると何とかなる。その場その場で、自分なりに楽しむ工夫をするから、大抵のことは楽しくできる。そんな感覚でやっています。
その裏には「死ぬときにふり返ったら、今の悩みや迷いは些細なことなのだろう」という死生観が、あるのかもしれません。父が52歳で亡くなったのですが、私自身もその年齢に近づいています。何か失敗しても、死ぬときに大きな傷にはならない。ならば思い切ってやってみようと。
「おかしな実験室」の皆さんは、オフィスではなくコラボベース NAGOYAやカフェ、自宅など、働く拠点を自由に選んでいますね。高木さんはどういう基準で、働く場所を選んでいるのですか?
1年目の2022年は、まず社内の人を知るために、会社へ行くことが多かったです。週のうち1〜2日はコラボベースで、あとは自社のオフィスで仕事をしていました。2年目は会社の人との関係性ができたので、コラボベースにいる時間を増やして、今度は外部の人脈を広げることに注力しました。3年目になると、コラボベースがもう自分の“ホーム”として、安心できる場所になりました。すると、カフェなどあえて別の場所にも行き始めました。2025年に入ってからは社外だけではなく、社内とのコミュニケーションを取るために会社にいる日を多くする……そんな調整をしています。
日々の選択で言えば、どうしても顔を合わせたい打ち合わせがある日は自社のオフィス、資料作成など集中して黙々と作業するときは自宅、ちょっと頭を切り替えるなど自分をリセットしたいときは、カフェなどを使います。コラボベースにいるのは、自分のお客様をお招きするときや他の会員さんと話をするなど、外部の方とつながりたいときですね。
新しいものを生み出すには、新しい人と会う方が、新たな考えや情報が入ります。 続けていきたいと思っています。
このような柔軟な働き方を続けてきて、高木さんのライフスタイルにも変化はありましたか?
大きく変化しています。以前は仕事とプライベートを「切り分ける」意識が強かったんです。でも今はほとんど境界がありません。
例えば、春日井製菓に入る前は「週末は会社の人に会わなくて済む」と思っていました。しかし、今は普通に仕事仲間とマラソン大会に出たり、サウナに行ったり。「いわゆる仕事の仲間なのか、プライベートの友人なのか」を区別しなくなりました。
結果的に、私の人生は豊かになったと思います。仕事の延長がプライベートになったり、その逆もあったり。これはおかしな実験室長の原の影響が大きいですね。「面白いことは全部やってみよう」と巻き込んでくれる人なので(笑)。
 Photoby 荻野哲生
Photoby 荻野哲生
お仕事をされる上での「やりがい」を感じる瞬間は?
「誰かがすごく喜んでくれたとき」です。 例えば先日、商品開発のメンバーが「新商品をどこかで売ってみたい」と言っていたので、イベントで販売機会をセッティングしたところ、すごく喜んでくれました。「おかしな実験農場」のワークショップでも、みんなが熱中して楽しんでくれたり。相手がすごく嬉しそうにしている瞬間が、もっとも達成感を感じる時です。
高木さんが働く上で「これはゆずれない」というものは何ですか?
お互いのリスペクトですね。そこが欠けてしまったら、もうその仕事は続けられないでしょう。反対に、リスペクトがあれば、大変な職場でもがんばれます。これは私の中で一貫していることだと思います。
まとめの編集会議
編集部の木下とライターの小越が取材を振り返って深堀りします。
木下:大先輩ですが、高木さんの「やってみる」精神が素敵だな、と思っているんです。コラボベースでお会いすると、どんな会合にも「行ってみるわ」といって、軽やかに出かけていきます。
小越:以前取材をさせていただいたコジロウさんも「考える前に動いてみよう」とおっしゃっていたとおり、苦手なことやわからないことでも「やってみる」は、楽しめる大人になる秘訣なのかもしれませんね。
木下:はい。高木さんは、その場を楽しくする工夫をしている、とおっしゃっていましたね。先ほどの「おかしな実験農場」のプロジェクトでもお知り合いを積極的に呼ばれていたのもその1つなのかなあと思いました。
小越:そうですね。それに、室長の原さんは周りを巻き込んでいく力がある方のようなので、一緒に「おかしな実験室」を作っていくうえで、高木さんの中で変化するものがあったのかもしれません。
木下:4業種4職種というキャリアも、「やってみる」の結果なのかな、と思いました。
小越:「自分はこれしかできない」ではなく、どんどんチャレンジして、ほかでは真似できない組織的な強みを増やして来られた印象です。
ただ、まったく新しいことばかりをしてきたというより、少しずつ仕事をずらしてきた感じですよね。1社目でSEと営業を経験し、2社目は営業と人材、3社目は人材と広報を経て、今に至る。入試の広報と企業広報では、だいぶ勝手が違うでしょうが、エッセンスとして共通するものはあるでしょう。
木下:なるほど。そういうやり方なら、経験値を活かしながら、自分の幅を広げていけますね!